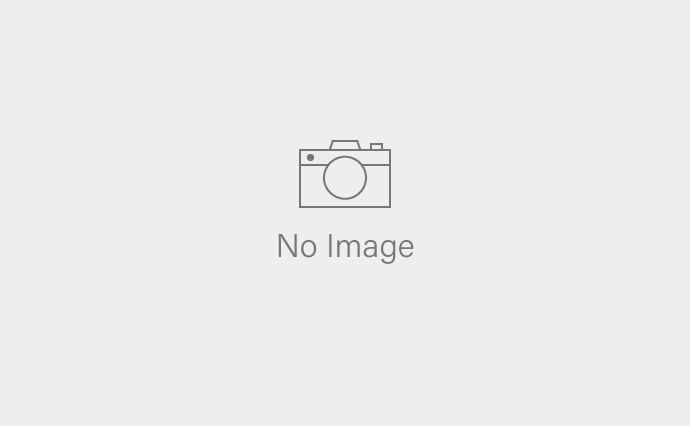状況
亡父Aさんの負債について相談したいと事務所を訪れたのは、その妻Bさんと長男Cさん 、長女Dさんの三人連れでした。
3ヶ月ほど前に債権回収株式会社からBさんとDさんに対して「9年前に亡くなった父Aが長男Cの負債の連帯保証人だった。Cの返済が滞っているから亡父Aの相続人であるBとDに弁済を求める」という内容の書面が送られてきたというのです。
妻Bさんと長女Dさんは,この書面により初めて,9年前に亡くなった父Aさんが長男Cさん(以下,債務者という。)の金4300万円余に及ぶ多額の債務を連帯保証していたことを知ったのです。妻Bさんと長女Dさんは、亡父Aさんからも主債務者である長男Cさんからも,そのような話は一切聞いていませんでした。。
これはCさんの住宅ローンの連帯保証債務であり,亡父Aさんが死亡した9年前の時点では通常どおり返済が行われていたため、このような関係が表面化することがなかったのです。
長男Cさんは、自分の借金のために母(Bさん)や妹(Dさん)に迷惑をかけたくないという一心でBさんやDさんには何も言わないで、債権者へ負債の10分の1程度を返済し、今後も分割払いするという和解を相談日の直前にしていました。つまり消滅時効は中断されています。
司法書士の提案&お手伝い
何もプラスの財産を相続していないBさんとDさんが突然に亡父Aさんが生前に行った連帯保証債務を相続して、金4000万円以上の負債を抱えることになり、このままではBさんもDさんも亡父Aさんのために破産するしかなくなってしまいます。
相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。 この期間を熟慮期間といいます。Bさん・Cさん・Dさんは、共に父の死をその日のうちに知り、それからすでに9年近く経っていています。しかも債権回収株式会社から手紙を返済を求める手紙を受け取ってから間もなく3ヶ月になるという時点の相談です。大変難しい事案でしたが、その旨をBさんもDさんにも伝えたうえで、相続放棄の申述書を作成、被相続人である亡Aさんの最後の住所地である家庭裁判所へ提出を代行しました。申述書には、事実に即して、次のような一文を記載しました。
「被相続人である亡Aの相続開始時には不良債権ではなかったからとはいえ、約9年もの間、債権者からは相続人である妻Bと長女Dには何の連絡もなかったのだから、BとDには相続財産の重要部分である本件債務を現実的に知る術はなかった。しかしながら本件債務の存在を知っていたならば,当然相続放棄をしていた。申述人としては,早期に相続放棄手続きを行う機会を逸したことが,申述人の責めに帰すべき事由と考えることができない。」
結果
BさんとDさんの相続放棄の申述書は、受理されました。そのためBさんとDさんは亡父Aさんが遺した負債は請求されません。自己破産せずに済みました。
物事の解決には、その時でしかできないこともあります。思いがけない出来事で困ったら、それを放置しないで、速やかに専門家に相談して頂きたいです。
ここでは、借金等のマイナスの財産を相続しない方法に関して、ご説明いたします。
相続放棄とは
マイナスの財産である借金を相続aしない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。
相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしで相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは相続放棄したことにはなりません。放棄すると言った人の分割割合を「ゼロ」にする合意ができただけの話であり、法的な意味の放棄とはなりません。遺産分割協議は、分割の割合や仕方を協議するものです。放棄を宣言することはできないのです。
限定承認
遺産の全てを受け継がない相続放棄とは異なり、相続人が一定の留保をしたうえで相続をする意思表示が限定承認です。
一定の留保とは、「相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ」というものです。
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄・限定承認の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
とはいえ、3ヶ月経過後でも相続放棄の手続を行うことは不可能ではありません。
保証債務があったら
相続を承認した後や、相続放棄・限定承認の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)